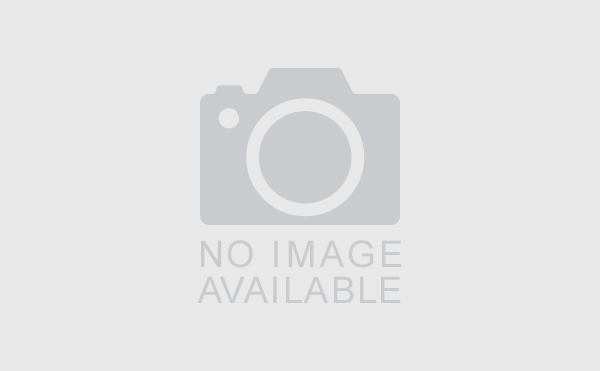使える介護保険へ
11月14日小竹雅子さん(市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰)による学習会を開催しました。
日本は2018年全都道府県が高齢化率21%を超え、5人に1人が65歳以上の超高齢社会に突入しました。2025年団塊の世代がすべて後期高齢者(75才)になります。
介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、2000年からスタートし3年ごと制度の改定がされてきました。介護保険の認定は、要支援1・2と要介護1 ~5まであり数字が大きいほど支援や介護がより必要となります。
当初の介護保険制度は、介護認定者が介護保険の支援の対象者として1割負担で家事介護やデイサービスなどが受けられる制度でした。
しかし現在は介護認定者の要支援1・2の人は、市区町村の地域支援事業の対象者として介護予防サービスになります。地域支援事業サービスの内容は、市区町村ごとに財源や施策により違いがあります。
更に2027年制度改定では、①介護認定者の要介護1・2(認知症も混在)の人も、市区町村の地域支援事業の対象者となり介護予防サービスへ、②現在の原則1割負担から原則2割負担へ、③ケアプランの有料化などが検討されています。 高い介護保険料を支払っても、介護サービスが受けづらい、受けられない制度への改定となることが危惧されます。
高齢者の介護を「社会全体で支え合う」目的が「家族の介護に頼る」方向に向かっているとしか考えられず、何のための介護保険制度でしょうか?
全国で介護や看護のための離職者は11万人(2022年総務省)に及んでいます。労働人口不足への更なる影響や介護虐待など深刻な社会問題です。また離職者は老後の年金受給額の減少に繋がり深刻です。団塊の世代が後期高齢者となり、今後益々介護保険制度の充実が必要な時です。税金の投入を大幅に増やし、誰もが安心して地域で暮らしていける介護保険制度の充実を求めていきます。 (斉藤)