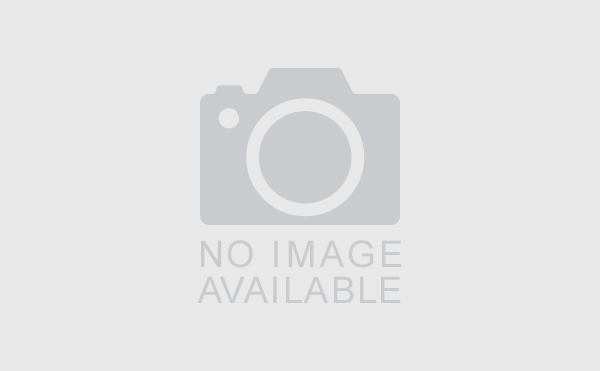2025国際協同組合年フォーラム報告と感想
7月7日に開催された2025国際協同組合年フォーラム「協同組合発、子ども・若者が豊かに生きられる社会をつくる」に参加しました。
はじめに基調講演「ひとりにしない」という支援(奥田知志さん:牧師、認定NPO法人抱樸理事長)」がありました。許してもらわなければ、助けてもらわなければ生きていけない「弱者共存」が人間社会の基本ベースというお話から始まりました。たどり着いたら断らないという抱樸(ほうぼく)で、心も体も傷ついていたA子さんとの出会いと成長に伴走支援したことで分かったことなど伺いました。「どうでもいいいのち」が口ぐせだったA子さんが人と関わることで「残念ながら死ねんなあ」と言うように成長したそうです。人は生まれる場所を選べません。人が育つ環境の大切さを思いました。
続いてのパネルディスカッションでは、はじめに「学校に行かない子どもが見ている世界」(西野博之さん:認定NPO法人フリースペースたまりば理事長)の報告がありました。「子どもの権利」の視点というお話から始まり、プレーパークで実践してきたことやそこから見えてきたことを話してくださいました。不登校35万人時代。150年前に明治政府が富国強兵政策の下で作り出した「学校」。社会は大きく変わっている。「学校」そのものを問い直す時期に来ているというお話から、公立学校の改革と並行して、「協同組合の学校」は作れないだろうか?という提案までありました。
次は「教育・学校を変える、地域社会で子どもたちを育てるとは」(前川喜平さん:現代教育行政研究会代表)の報告がありました。日本の子どもの幸福度と自己肯定感の低さや自殺する若者の増加があるが、子どもも教師も生きづらい学校の現実があり、不登校・病気欠席、病気休職が激増している。学校はもっと自由なものであり地域のものなのに、子どもと教師を苦しめているのは国家主義と新自由主義の教育政策にある。子どもたちは社会の中の存在であり、社会全体で支えるべき存在だと話されました。
最後にオランダから、「子どもたちに自由と責任を育てる教育」(リヒテルズ直子さん:)の報告がありました。オランダでは自分を出せる自由があり、異なる立場の者が自分の立場からの意見を徹底的に出し合ったうえで、対立ではなく話し合いで妥協の道を探ることをします。学校は社会に向けて子どもを育てる場所なので、子どもたちも話し合いを通してwin winの道を探ることを学ばせ、自由と責任の意味を教えようとしています。リヒテルズさんの失敗談として、学校の懇談会に子どもを連れないで行ったところ、オランダの懇談会は教員と子どもの間で直接行うのもで、学びの主体は子どもであり、学びの責任は子ども自身にあると知ったそうです。その他のご自身の経験からのお話は自分らしく生きていくための教育や社会のあり方を考えさせられるものばかりでした。
フォーラムの最後に宣言「子ども・若者が豊かに生きられる社会をつくろう!」と提言1.学校と教育に関する提言 2.協同組合、市民活動への提言 3.地域社会における協同組合の活動、事業としての提言 の発表がありました。
協同組合年フォーラムに込められた「混迷する世界、社会の中で地域に暮らす人々が主人公で将来にわたって地域で暮らし続けていけるために協同組合を用具に発展させよう」というメッセージが強く感じられる集いでした。
個人的な感想です。帰路、組合員活動を始めたころのことを思い出しました。生活クラブのことを「民主主義の学校」と話す方もいました。折に触れ「自主運営・自主管理」とか「おおぜいの私」という言葉を聞き、意味を考えながら組合員活動をしてきました。知らないこと、わからないことが多くて活動しながら学びました。しかし子どもの時から民主的な社会の中で育ってきたといえない私は、いまだに中途半端な気持ちがあります。小さい時からの環境は大事だとつくづく思いました。地域社会の一員としてできることは何かなと考えていけたらと思いました。(市川)